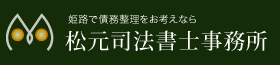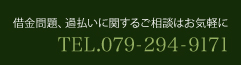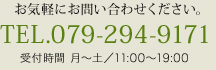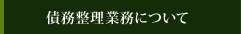
- 姫路で任意整理をする
- 姫路で相続放棄をするには?
- 姫路で民事再生を司法書士が説明
- 姫路で自己破産をするには?(督促を止める)
- 姫路で任意整理・過払金
- 業務の流れ
- よくある質問
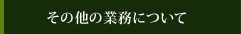
- 姫路での相続登記費用:姫路の司法書士
・住宅購入、贈与、相続など - 姫路で会社設立登記
・会社設立、役員変更、定款の見直しなど - 姫路で相続を考える
- 成年後見制度を姫路の法書士が詳しく説明
- 敷金問題
- 退職代行サービス:姫路の元労働基準監督官による

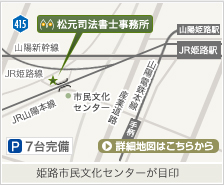
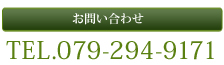
![サービス対応エリア:[兵庫県]姫路、加古川、高砂、加西、姫路、龍野、赤穂、相生その他周辺](https://saimuseiri.biz/common/img/s_area.jpg)
貸金業規制法の骨子まとまる
金融庁は24日、「改正貸金業法完全施行に向けた対応」について、貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)の座長試案(座長・大塚耕平金融庁副大臣)をPTメンバーに提示した。今後、関係省庁等のほか、多重債務者対策本部有識者会議の意見も踏まえ、最終案確定に向けて可及的速やかに検討を進めるとのこと。
改正貸金業法は、多重債務問題が深刻な社会問題化したことを受けて、平成18年12月に、国会において全会一致の賛成により成立した。同法は、貸し手への適切な規制を通じて新たな多重債務者の発生を防ぐ一方で、急激な与信の引締め等が生じないように段階的に施行されてきたが、本年6月までの完全施行に向けて、その附則において、「改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討結果に応じて所要の見直しを行う」旨が規定されていた。そして、この間、関係省庁である金融庁、消費者庁の副大臣、大臣政務官及び法務省の大臣政務官から構成される「貸金業制度に関するPT」が設置され、次のような論点をまとめた。
【改正貸金業法の完全施行に関する論点】
1.改正貸金業法の経緯・状況
(1)経緯(略)
(2)状況
借り手の状況
・5件以上無担保無保証の借入れを行っている者の割合は減少
-14.7%(19/3)→5.8%(21/12)
・1人あたりの借入残高も減少
-116.9万円(19/3)→81.5万円(21/12)
・上限金利の引下げ前に、消費者金融の貸付金利は低下
-23.0%(18/3)→17.8%(21/9)
・全都道府県、9割の市区町村で多重債務相談窓口が整備済み
・一方で、完全施行により、借り手の5割程度が総量規制に抵触する可能性
貸金業者の現状
・貸金業者は、業者数が近年大幅に減少
-過払金返還負担の高止まり、貸付金利の引下げ、新規与信の厳格化が主たる要因
・消費者ローン大手4社の損益等も厳しい状況
2.貸金業の位置付けについて
(1) 個人に対し、無担保・無保証で迅速に小口の資金を貸付け
-銀行等は、企業金融が中心。個人向けも、住宅ローンなど担保があるものが中心で、貸付審査にも一定の時間が必要。
(2) 事業者向けについては、信用力が低い事業者に対しても、迅速に資金を貸付け
-銀行等は、貸金業者と比較すると、<1>貸付審査に時間がかかる、<2>ある程度の信用力を有する企業を融資対象とする、<3>担保・保証を必要とする場合が多い、などが特徴。
(3)貸金業法により、貸金業者を(ミドル・リスク、ミドル・リターンの)消費者金融市場の一つの重要な担い手と位置づけ
3.日本における消費者金融の現状と将来像等
(1)我が国の金利の実勢は、「ふたこぶ」の状況
(注)低金利帯(4%以下)では銀行等が主として貸付けを行う一方、貸付金利の低下など状況に改善は見られるものの、高金利帯(20%程度)では貸金業者が主として貸付けを実施
(2)今回の改正により、上限金利の引下げ及び貸金業者に係る総量規制を実施
(3)貸金業者の適正化と銀行等の個人向け貸付けへの一層の取組みにより、「ひとこぶ」となる消費者金融市場の形成を期待
以下、「総量規制に抵触している者の借入残高を段階的に減らしていくための借換えの推進」「個人事業者の安定的な「事業所得」を総量規制の「年収」として算入」など、「借り手の目線に立った10の方策」をまとめるなど、きめ細かい内容となっている。つまり、今回の「見直し」のポイントは、「健全な消費者金融市場の形成」にあり、そのためには、消費者向け貸付けについて、「銀行・信金等による社会的責任も踏まえた積極的な参加が望まれる」と結んでいる。ゼロ金利政策が15年も続く中、消費者金融だけが10数%という「高金利」、しかもメガバンクが系列に消費者金融を抱え、事実上、消費者金融市場を制覇しつつある現状を、今回の「見直し」で、どのように改善、改革できるのか注目したい。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
10.04.01
この記事のカテゴリ:晴れ時々ブログ