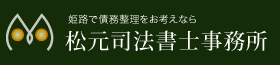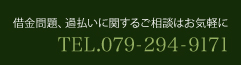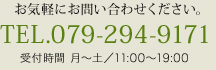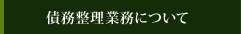
- 姫路で任意整理をする
- 姫路で相続放棄をするには?
- 姫路で民事再生を司法書士が説明
- 姫路で自己破産をするには?(督促を止める)
- 姫路で任意整理・過払金
- 業務の流れ
- よくある質問
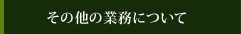
- 姫路での相続登記費用:姫路の司法書士
・住宅購入、贈与、相続など - 姫路で会社設立登記
・会社設立、役員変更、定款の見直しなど - 姫路で相続を考える
- 成年後見制度を姫路の法書士が詳しく説明
- 敷金問題
- 退職代行サービス:姫路の元労働基準監督官による

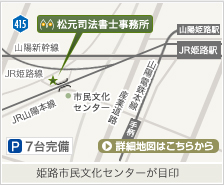
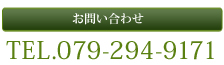
![サービス対応エリア:[兵庫県]姫路、加古川、高砂、加西、姫路、龍野、赤穂、相生その他周辺](https://saimuseiri.biz/common/img/s_area.jpg)
東京高決令元11.25
(事案の概要)
被相続人にの死亡後2年後に一度相続放棄の申述を行ったが相続放棄を受理されず、却下となり、申述者はこれを不服に思い即時抗告しました。
抗告後 一転して、原審判取り消し、受理される結果となり、無事相続放棄の申述が受理される事になった事件が元となっています。
(事案の詳細)
亡き被相続人にの姉の子供3人が法定相続人である相続放棄事案で、被相続人の負債に対し、相続人が面倒に巻き込まれる前に、その相続人姉の子3人のうちの代表一人だけが、相続放棄を家庭裁判所に対し申述し残りの2人は代表が相続放棄すればそれだけで足りると解釈し、残る2人は申述しなかったのです。
家庭裁判所に提出された相続放棄申述書には、その代表一人の名前だけが記載されてありましたが、何故か収入印紙は3人分入ってありました。
そして時がたち2年後のある日、市役所から電話があり、被相続人の固定資産税2万9千円が未納であるという通知が来ました。
相続放棄は、代表の相続人が行ったのに通知が来たのです。
そこで相続人の2人は、初めて全ての相続人が全員が相続放棄が必要であることを聞かされるのです。
そこで、残りの相続人2人も慌てて、管轄が同じ家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことにしました。
ところが、家庭裁判所は、相続を知ってから2年が経過していたため(前橋家太田支審令元9.10)民法915条が1項が定める相続放棄の熟慮期間について、市役所から一番初めに書類が来た日付を起算日とすべきであり、本件の相続放棄の申述は、
それ以降になされているとして、申述を受理せず却下したのです。
それを覆すために。2人は、慌てて家庭裁判所に抗告しました。
そこで高裁で本事案は、再審理され幸いなことに
裁判所は、以下のように決定を取り消し、受理することになりました。
理由は以下です。
相続人の2人が相続放棄が遅れた理由は、自分たちの相続放棄の申述は、もう既に完了していると誤解が大きな原因でなおかつ、
被相続人の財産についての情報が不足しておりこれも、被相続人との疎遠な関係が起因していることも考えられ、このような特別の事情を考慮すれば、
民法915条1項の熟慮期間の起算日は、固定資産税の具体的な額についての説明を市役所の職員から受けた時期から進行を開始するものと解するのが相当であると、
一度家庭裁判所で不受理が決定した事案を、高裁が取り消して受理することが適当であると示した事案です。
これには続きがあり、以下理由
相続放棄の申述は、相続放棄の実体要件が具備されることを確定されるものではない一方
これを却下した場合は、民法938条の要件を欠くことになり、
相続放棄したことが主張できなくなることを考えれば家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合を除き相続放棄の申述は、受理することが相当であると、
分かり易く言い換えると、
相続放棄というのは、やがて人が死亡すると確実に皆に訪れる可能性が高い手続きの一つで、それを厳格な法的手続き要件に拘束してしまうことで、被相続人の負債を帳消しにする唯一の手助けとなる相続放棄を機能不全に貶めてしまう可能性が高い。
であるから、相続放棄の要件は可能な限り法的要件を広くし、受理するのが相当である。
上記のように理由まで述べられています。
一応、相続放棄申述事件は、高裁で却下すべきことが明らかな事例を除き受理すべし
とあるわけですので、これが一応の指針となり、相続放棄の申述があれば基本は、受理すべきで余程のことでない限り不受理は出来ないとなろうかと思われます。
しかし、上記の例は、代表だけが相続放棄をすれば足りると誤解があり、3人分の収入印紙を同封してきていることも考慮された可能性が高く、決して一概に安心できるものではないのも事実です。
電話 姫路 079-294-9171
25.03.16
この記事のカテゴリ:晴れ時々ブログ